なか2Cおもちゃ工場⑤
校内授業研振り返りより…
1.主張点
少人数グループで向かい合って活動できる学習環境により考えを伝え合う会話が活発になり,友だちや自分の気付きをおもちゃ作りの工夫に生かそうする子どもの姿が見られる。
2.授業の実際(授業記録より)
ⅰ授業者の指示
T:「腕によりをかけて試作してきたおもちゃを紹介する時間です」
ⅱ各グループでの紹介タイム(手で動かすおもちゃ①グループ)
C:「言うこと覚えてない」
C:それぞれが違うことを話す・隣同士で話す
C:「つけたほうがいいと思って…」「見せて!」
C:「終わったらなにすんの?」×5
T:「ここグラグラするからアドバイスしたげてよ」
C:「二重にしたら?」

ⅲ全体会議・その1(タイヤが取れることと回らないこと)
T:「ちょっと!どもならん(和歌山弁:どうしようもない)問題が発覚してるから,あっちで緊急会議!」
C:「タイヤが取れて困っています」
C:「棒を長くした方がいい」「テープで付けたら…」
T:「タイヤが回らないという問題もあるわけや」
C:「ストローは回らないからストローの中に竹ひごを通しているから…」
C:「(タイヤが取れないようにするために)ここに輪ゴムをつけたら?」

ⅳ全体会議・その2(まっすぐ走らないこと)
T:「ここで大問題やったのは…走らす時?」
C:「まっすぐ行かへん」
C:「磁石を真ん中らへんに」「真ん中にしても横に動くで」「重さの問題?」
T:「けんたろうに聞いてみよう…まっすぐ走ってたな」「何が違うでしょう?」
C:「あ~!ストローか!」
C:車軸の付け方の話→カット

ⅴ学びの振り返り
C:「すごいおもちゃを作っていた」→「とかげのおもちゃが電車のような音を鳴らす」
C:「あかちゃんブーブー」(風船が膨らまず実演なし)
C:「重りを付けていたのがよかった」
C:「あいちゃんのがすごい!」
T:「すごいよね!…終わります!」
C:「え~!」
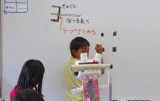
3.研究協議会より
(1)授業者の振り返り
・報告書を書かせたため,それを話さなければならないと思ってしまっていたので,紹介に入りにくかった。
・「紹介しよう」の指示が不適切だったか。工作をし出すなどの姿をイメージしていたが…。
・Oの字型の座席は失敗。Uの字型にすべきだった。
・取り上げた課題は,音が鳴るおもちゃグループの子どもたちには酷だった。
(2)主な協議内容(質問・意見・感想含む)
①学習環境,少人数,コミュニケーション
・「あれ」などの言葉が多い低学年だが,学習環境や具体物により,会話が成立していた。聞きあう姿も見られた。いい距離感で,自然発生的に共有できていた。
・教室にいろんなモノがあるので取りに行って工作する子どももいた。
・人数が多いと意見が離れてしまうが,少人数での活動がよかった。しかし,何を話すかを明確にしておく必要がある。また,グループ分けの理由を細かく,明確にしたほうが…。
・話が5分もスタートしないチーム(手で動くグループ②)があったが,教師が質問に入ると,それをきっかけに話すようになった。質問されると答える子どもたちがいた。「しかけ」がキーワードで,話を始めるスイッチのようなものだ。
・グループ(少人数)になるまでの場の持ち方に工夫は必要。グループでの交流は大切。
・音が鳴るおもちゃグループは,ビーズの音ぐらいが主な内容。そんな中でも,動くチームの話に入っていった女の子はよくがんばった。
・グループでの活動と全体会議の場があったが,分けるのがいいのか,あのままグループですすめるのがいいのか…。
②可視化,共有化
・気付きを教師が先に共有してしまっていた。
・ストローと竹ひごの工作を教師がしたが,子どもたちみんなで試してみるべきだった。子どもたちが実際に試してみることで共有できるのではないか。
・磁石の話などは,なおさらみんなでやってみる方が良い。感覚的にわかるということも期待できる。
・つぶやきが少なかった。また,教師が拾わなかったため,つぶやきが流れてしまった。
・話し合いの必然性がほしい。具体物を持っているのだから,話し合うだけではなく「やってみる!」ということで共有できるのではないか。本時では共有できていなかった。聞いていた子どもはわかっていなかったのではないか。共有できるからこそ,再認識できる。
③指導,支援,その他
・着目児を置くべき。発言の多い(かしこいことを言う)子どもが話すことで,正解だと思って他の子どもが話さなくなる。言い出しにくい子どもを大切にするべき。
・教師が板書した図は,わかりにくいので意味がない。実物で納得できる。
・悩みを明確にすべき。「困ったカード」など。
・図工や理科と何が違うのか?
(3)指導助言(船越先生)
・生活科とは…再利用できる物を利用することで生活を豊かにする(楽しいおもちゃ)ことができる。またそうしようと思う心を育てることができるのが,図工や理科との違い。
・材料が多い方いとそれぞれの特質を活かして工作できるのでいい。材料との出合いから工夫して活用していくという幅広さがあるが,拡散するために焦点化が難しいという短所もある。
・作ることを通して知ることができる「しかけ」がある。修正していくという目的もあるものだった。音が小さい
