「音楽科」を考える
コラムvol.1
附属小教員が,教科について自由に語る!
北川 真里菜
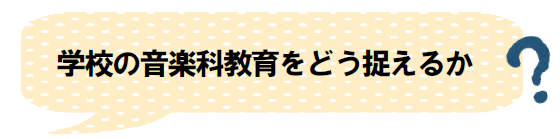
私が受けてきた専門的なレッスンとは異なり,学校では,音楽が得意な子や苦手な子,様々な実態の子供たちが共に学びます。この環境が大変興味深いものです。私の音楽科授業の信念には,「全員参加」が軸としてあります。苦手な子にも音楽の楽しさを知ってほしいですし,得意な子も,音楽の奥深さを知ってさらに知的好奇心を高めてほしいと思います。そのために私は教師としてコーディネーターを務めたいと考えています。主役は,子供たちなのです。
アメリカやイギリスの研究では,音楽科の学習が充実していると他教科の成績も上昇したり,音楽の能力以外の認知能力や社会生活での様々なスキルの育成,強いては生活の質の向上にも貢献したりすることが分かっています(2019,森尻*1)。
*1 https://www.yamaha-mf.or.jp/onkenscope/morijiriyuki2_chapter2より引用
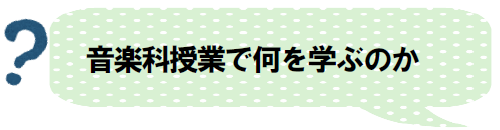
学習指導要領では,「生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる力」を育成することが音楽科の目標であると示されました。「音楽で学んだことが生活や社会でどのように役立つのか」,という視点が重要となります。
音楽科授業と聞いて想像されるのは,歌を歌ったり,リコーダーを吹いたり…といった風景ではないでしょうか。これが目的化されてしまうと,「学校教育じゃなくてもできるんじゃない?」という話になります。「習い事でやればいいじゃないか」と。2017年の学習指導要領改訂で特筆すべきなのが,音楽科の技能について,「創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を身に付ける」と示されたことです。要するに,「上手に演奏できるようになろう」と技能だけを取り出して指導するのでなく,子供たちの「表現したい!」という思いとどうリンクするか,という視点が大事なのです。
例えば,ある曲を授業で扱うときに,この曲で子供たちに何を学ばせたいのか,を考えます。6年生の『ラバーズ・コンチェルト』は,音楽には主役(主旋律)や,全体を支える役割(低音)など,それぞれのパートの役割があることを学ぶのに適した教材です。この内容を学ぶことを目標に掲げると,子供たちは,「主役の役割を果たすために,どのように演奏すべきか?」を創意工夫し,演奏することになります。その学びを生かして,「主役」「和音」「低音」の役割で音楽をつくろう,などと音楽づくりを行うこともできます。これらの学びは,他の教材曲や,日常生活で流行の音楽を聴く時などにも役立つ汎用的なものとなります。
このように,「リコーダーで吹きましょう」ではなく,「何のために演奏するのか?」を子供たちと共有し,どのような概念を学び,それが実際にどのように使えるのか?を,子供たちが実感できるようにしています。
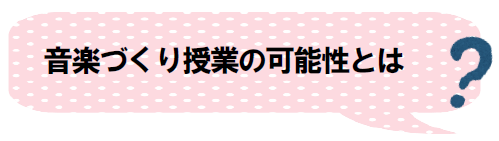
音楽科では「歌唱」「器楽」「音楽づくり」「鑑賞」の4領域の内容をバランスよく指導することが求められています。ですが,既につくられた曲を再現する活動に重きが置かれがちで,特に「音楽づくり」の実施率の低さは音楽科の課題として挙げられています。
急に「曲をつくりましょう」と言われても,大人でも困惑しますよね。私は,歌唱や器楽で学んだことを生かして音楽をつくるなど,4つの領域を横断して,子供たちが創造性を発揮して音楽をつくれるようにしています。また,音楽をつくったからこそ得られた実感を伴った理解が,鑑賞で生かされる,といった往還も考えられます。試行錯誤しながら世界にたった一つしかない音楽をつくるという経験は,正解がなく変化の激しいこれからの社会を生き抜く子供たちにとって,有意義なものであると考えています。
私の授業では,既成の楽器のみならず,総合的な学習の時間に子供たちが拾ってきたごみで楽器を作って音楽をつくったり,コンビニエンスストアの入店音を分析して学校の開場曲をつくったり,言葉や動物の鳴き声で音楽をつくったりなど,子供たちの身近な音や音楽を用いた音楽づくりを展開しています。リコーダーや鍵盤ハーモニカと並んで,子供たちの生活の中のものが表現媒体となり得ると考えているのです。椅子や机などの身近なものを見て,「どのような音が出るのかな?」と考えながら日常生活を送る子供たちの姿を想像すると,とてもわくわくします。
本来,音楽とは子供たちにとって身近なものです。音楽科授業と,生活や社会の音や音楽とが分離することのないよう,その接点を探りながら,「学校で音楽を学ぶ意味」を問い続けていきたいと思っています。

